| ハ ノ イ Slide show |
| 首都ハノイは人口約250万人でホーチミンに次ぐ2番目に大きい都市である。11世紀の李朝(りちょう)はこの地を都と定め農業地帯を統治する拠点とした。李朝の成立以降1802年にグエン王朝がフエに都を移すまで王都として繁栄し1831年に現在の名称になった。1873年以降フランスの植民地であったが、1954年ホー・チ・ミン主席が率いるベトナム民主協和国軍がフランスに戦勝しハノイは北ベトナムの首都となった。1960年アメリカとのベトナム戦争が勃発し橋などの交通施設を中心に爆撃を受けたが、1975年アメリカに勝利しハノイは南北統一ベトナムの首都となった。ホー主席は「独立と自由ほど尊いものは無い」という名言を残し、南北統一を見ることなく1969年79才で死去(病死)した。市内観光 文廟 一柱寺 ホーチミン廟 水上人形劇 07.4.24 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| 「ハノイ上空」から見た町並みは、緑一面の「水田」に囲まれていた。 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 沿道の電柱には無数の電線が絡み付き「豪華住宅」も建っていた。 |
|
| 「ドリアン」を売っている八百屋があった。このフルーツは強烈な悪臭で知られるが、一度食べたら病み付きになるそうだ。 |
|
| 軍服に似た制服姿の「警官」が、辺りを威圧するように立っていた。 |
|
 |
 |
 |
|
|
| 「交差点」に沢山のバイクが信号待ちをしていた。停止線の前に整然と並んでいるので、中国とは異なり規範意識は高い。 |
|
| 道路には無数の「バイク」が爆走していたが、暴走族はいない。 |
|
 |
 |
 |
| 「マスク」をしている人はいるが、誰もヘルメットを被っていない。だが、最近ヘルメットの着用が義務化されたので、現在は様変わりしているであろう。 |
|
| 「スクーター」も沢山走っている。ここは中国に比べ、若者が多いので自転車は少ない。 |
|
| 土産店では学生が「刺繍制作」の実習をしていた。全員上手だったから、特別に選ばれた学生なのであろう。 |
|
 |
 |
 |
| 「絵画制作」の実習もしていたが、玄人並みの出来映えであった。これらは土産品として販売されている。 |
|
| 昼食のレストランで沖縄の「花」を奏でる「可愛い演奏家さん」と記念撮影する。大きな帽子は沖縄の花笠と似ていた。 |
|
| 小規模な「火力発電所」があった。何時かは原発を持つのかも知れない。 |
|
 |
 |
 |
|
|
| ホテルの都合で最上階にある豪華な部屋に宿泊できた。ラッキーなVIP待遇であった。 |
|
|
 |
 |
 |
| ホテル最上階からの「ハノイ早朝の街並み」は平穏であった。 |
|
| 町の中心にある「ホアン・キエム湖」の水面に、宿泊したホテル(左)が美しく写っていた。 |
|
| 整然とした「ハノイ空港」から、次の観光地フエに向かう。 |
|
| 文廟は(バン・ミョウ)は儒教の祖、孔子を祀(まつ)った廟(びょう)で1070年に創建され1076年にはベトナムで最初の大学を併設した。 |
|
|
 |
 |
 |
| 「文廟門」の両側の柱には孔子の教えらしき文が書かれている。当初は木造であったが、その後石造に改築された。 |
|
| 亀が背負った「石碑」は15〜18世紀の科挙試験合格者名簿で、82基に1000名の名が刻まれている。合格者の最若年齢は13歳で最高齢者は83歳であった。また合格者は皇帝の娘と結婚できたそうだ。 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
| 隣にある「民芸品店」では、売り子さんが「アオザイ」を着て接客していた。 |
|
 |
 |
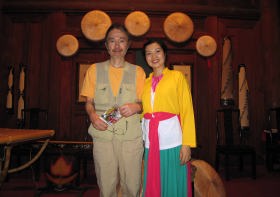 |
|
|
|
| 美人演奏者さんと「並んで記念撮影」した。購入したCDを見るだけで名演奏の調べを思い出す。 |
|
| 一柱寺(いっちゅうじ)は子宝に恵まれなかった李太祖が、慈母観音の夢を見た後に子を授かった感謝から1049年に建造した寺である。ハスの花が咲く姿をかたどった国内最古の建造物である。現在柱はコンクリートに変えられている。 |
|
|
 |
 |
 |
| 池の中に1本の柱を足として、その上に3m四方の小さな「ほこら」がある。親子連れが拝観に来ていた。 |
|
|
|
| ホーチミン廟はベトナム建国の父・ホーチミン主席の廟(びょう)で、1969年に79歳で死去した後1975年の建国記念日に建てられた。 |
|
|
 |
 |
 |
| 「ホーチミン廟」は警備が厳しくカメラやバッグの持ち込みは禁止である。 |
|
|
| 「フランス人観光客」がガイドの説明を聞いていた。反米意識が強いのでアメリカ人はいないそうだ。 |
|
| 水上人形劇はホアン・キエム湖北岸近くの人形劇場で1969年設立された。ベトナム北部で11世紀頃から水田で始まった人形劇が元になっている。 |
|
|
 |
 |
 |
| 水田に似せた「舞台セット」の後ろに人形使いが隠れている。左側には「楽団と弁士」が座っている。 |
|
| 人形使いが竹竿を使って「人形を操る」のだが、その見事な演技に言葉は分からなくとも見入ってしまう。 |
|
| 幕引きに人形を操っていた「人形使い一同」が紹介された。ずぶ濡れではないから、水中に潜って操っている訳ではない。 |
|
| BACK NEXT |